2025 年 2 月 4 日
- 中級
-

今週は、子供新聞を読みました。タイトルは「C'est quoi, la laïcité à l'école 学校でのライシテ ( 非宗教性 )ってなあに 」
ライシテは長い長い歴史上の衝突や思索のすえにうまれた考えです。一つの宗教を信じることも信じないことも自由で、その自由を保証してくれる原則がライシテです。同時にほかの宗教を尊重し、ライシテにかかわる法律を守ることも必要です La laïcité, c'est un principe qui garantit la liberté de croire ou de ne pas croire en une religion, dans le respect des autres et de la loi 。公立学校でのライシテは 1882 年に決められ、聖職者が教壇に立つことも、公立学校で宗教的な教えを説くこともなくなりました。

ライシテがあることで、生徒がどのような信仰をもっていても、その生徒は一人の生徒として平等にあつかわれます。それぞれの生徒は自分の考えを自由に述べることができます。ですが同時に、ほかの人の考えも尊重せねばなりません。また十字架やベールといった信仰のしるしとなるものを身に着けて学校に来ることもできません。
このようにライシテには市民権や平等、自由といった価値 les valeurs de citoyenneté, d'égalité et de liberté がふくまれています。学校の教室にライシテ憲章が張られているのは、ことことを忘れないようにするためなのです !! 以上、子供新聞からでした

ところで以前に、イスラム教のスカーフをかぶっていた公立学校の女子生徒が退学させられる…という出来事がありました。ライシテが排除の盾になってしまったといえなくもない出来事でした。
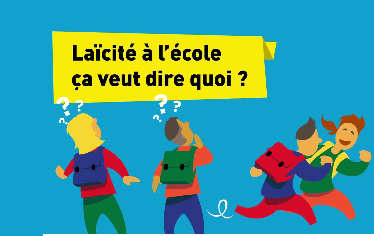
© 2025 milan Presse
- 上級
-

今週は『影泥棒 Le voleur d'ombres 』です。
前回は、男の子が食事を一切うけつけない理由を、「僕」が知ったくだりでした。その理由とは…
男の子が大事に飼っていたウサギが行方不明になったのですが、夕食後にお母さんが「今日のウサギの赤ワイン煮は美味しかった?」と皆にむかってたずねたからでした。その以来、男の子は食事を全くとれなくなったのでした。以上が「僕」が影をとおして知った理由です。ソフィーは、精神科医も解けなかった謎を、僕がどうしてわかったのか半信半疑でした。が、とりあえずは、男の子の容態を治すことが先決です。男の子の両親に、よく似たウサギを見つけてもらい、男の子の枕元に持ってきてもらうという目論見をたてました。
ただし院内に生き物をもち込むことはできませんから、夜中に秘かに決行することとなりました。…と前回はここまで。
* * *

男の子のお母さんが、ポケットにウサギをしのばせて、うまく病院に入ってきました。誰にも見つからずにすむ時間は最大20分。お母さんは男の子の病室に入り、男の子の額をやさしく撫でます。目を覚ました男の子に、僕が語ります。「逃げたウサギは生きていて、その子ウサギが生まれたのだけれど、子ウサギの面倒をみてくれる人が誰もいないんだ Ce petit lapin n'a plus personne pour veiller sur lui 」と。そしてお母さんが小さなウサギを男の子に差しだしました。男の子はゆっくりと手を伸ばし子ウサギの頭をなぜます。お母さんは、男の子に子ウサギを託しました Il avança lentement la main et lui caressa la tête, la maman le lui confiia 。僕は、男の子とお母さんとを残して病室を出ました。そして病室の前にいたお父さんにも、病室に入るよう促しました。お父さんは、僕に感謝するかのように、僕をだきしめました。ほんの一瞬の間、僕は自分自身のお父さんに思いをはせたのでした。
翌々日、僕は医局長から呼び出しを受けました。男の子の病室から子ウサギの毛が見つかり、男の子が事情を話してしまったからでした。

ちょうど局長のフェルンスタイン教授が助手や学生をひきつれて巡回していたので、僕もソフィーもその巡回に加わりました ...le grand patron ( = le professeur Fernstein ) assurait lui-même la visite matinale accompagné de ses deux adjoint. Je me joignis au groupe d'étudiants qui les suivait 。男の子の病室の巡回で、教授が「食欲をとりもどした子だね。朗報だね。」と言います。
すかさず精神科医たちが如才なく、自分たちの治療が功を奏したと説明します。が、教授は僕の方を向いて、「このように突如、回復にむかったのには、他の理由があるのではないか」とたずねます Et vous, dit Fernstein, en se tournant vers moi, vous n'avez aucune autre explication pour justifier ce rétablissment soudain ? 。僕はうつむいて、否定します。教授はなおも、それならやはり精神科医の治療のおかげなのか、と念をおすようにたずねるので、「それ以外に考えようがありません」と僕は答えます。教授は男の子の髪をなで、励ましの言葉をかけて退室しました。その後も巡回は続きます。が、巡回の解散のときに、教授は僕だけを呼びとめたのでした。次回は p143 の " Sophie ne se le fit pas répéter et me laissa seul en compagnie du professeur ...からです。
© " Le voleur d'ombres ", Marc LEVY, Edition Robert Laffont
2025 年 2 月 18 日
- 中級
-
 卸売市場レ・アル
卸売市場レ・アル今週から新しい教科書になりました !! 『フランス史のなかの「異人」たち 2 』 世界を変えた女性たち Du passé au présent, les femmes françaises qui on changé le monde を読みます。
第一課のタイトルは「ルイーズ=ルネ・ルディック Louise = René Leduc 」です。聞きなれない名前ですが、どのような人だったのでしょう。* *
レ・アル Les Halles はパリの胃袋とも呼ばれていた巨大な卸売市場です。レ・アルで働く女性たちはたくましく、歯に衣を着せない物言いで知られています (les femmes ) bien connues pour leur langage et leurs manières cavaliers 。おもにその女性たちが「パンを !! 」と叫びながらヴェルサイユ宮殿までの約 20 キロを行進をしたのだそうです。その行進の先導者がルイーズ=ルネ・ルデュックだったというわけです。フランス革命がおきた年のことでした。
 行進する女性たち
行進する女性たちベルサイユ宮殿では、警護隊とルイーズ達とが向き合い、緊迫した状況だったのだそうですが、行進仲間の数名が議長立会いのもと議場にはいり、王に人権宣言や憲法に署名を迫ったといいます。
のちにルイーズ=ルネ・ルディックは、投獄されますが釈放され名誉を回復。しかし投獄中に精神を患い 1802 年に亡くなったのだそうです。

© 『フランス史のかなの「異人」たち 2 』 朝日出版社
- 上級
-

今週は、ミュエル・バルベリ Muriel Barbery の『優雅なハリネズミ L'élégance du hérisson 』です。
前回は、私 ( = ルネ ) が、自分の文学や映画の好みを語るくだりでした。
私はいろいろなものに手を出しています。高尚といわれるものだけに接しているわけではありません。これは私が庶民出で、独学だったせいだと思っていました。ところが今朝、フランス・アンテール ( ラジオ ) を聞いていたら、けっしてそうではないことがわかり驚かされたのでした。とにかく私は、貪るように本を読み、映画を観、音楽を聴きます。ジャンルはこだわりません。スタンダールや⾰命前のロシアの作家は特に好きですが、それ以外は何でも手あたりしだいに読んでいます。犯罪小説ならヘニング・マンケルやマイクル・コナリーが手放せませんし、映画であれば ブロックバスター blockbusters つまり大ヒットしたものなら何でも OK です。・・・と前回はここまで。
***
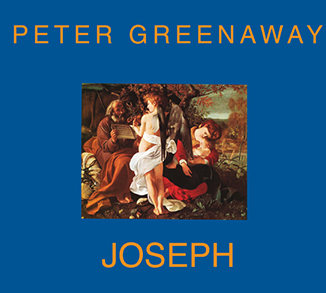
もちろんピーター・グリーナウェイの作品の審美性には憧憬の念をおぼえますが、ちょっとねむくなるのも確かです。これは第七芸術としての映画の宿命でしょう。
ところで今日、私はとある映画をもう⼀度観ようと思っています。1989年のクリスマスに観て以来、ずっとずっと我慢しつづけてきた映画ですから、私は今うずうずしているのです。
以上、「現代エリートたちの預言者」終り
- - - - - - - - - - - - - - - -
第九節 「赤い10月」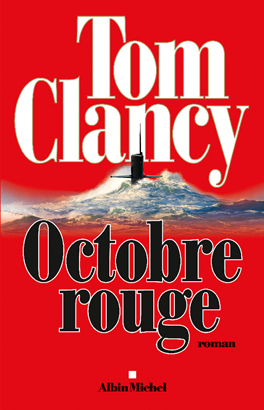
1989年。夫のリュシアンは病に伏して、いつ死をむかえてもおかしくない状態でした。リュシアンと私はその覚悟を共有していました。そして17ヶ月の闘病を経て、リュシアンはクリスマスイブの日に亡くなりました。
3 階に住むムーリス夫人が、マンションの住人に呼びかけ、管理人室の前に花輪を届けてくれました。なんの言葉もそえられていない花束でした。ムーリス夫人は姑としては厳しい人だったようですが、リュシアンの葬儀に唯⼀、参列してくれた人でした。
ムーリス夫人以外の住人にとって、リュシアンの死などとるに足らないことなのでした。持てる人たちにとって、持てる人の死はドラマであり理不尽なものなのですが、お金も処世術ももたない庶民の死などは、持てる人たちにとっては、他の生き物の死となんら変わらないものであり、ただ無に帰るだけなのです。
次回は、p86 の Que, comme chacun, nous puission endurer l'enfer et que ... からです。
© " L'élégance du hérisson ", Muriel Barbery , Editions Gallimard
2025 年 2 月 25 日
- 中級
-

今週は、『フランス史のなかの「異人」たち 2 世界を変えた女性たち』の第 2 課『ジョルジュ・サンド』です。
ジョルジュ・サンドは祖母から " ノーアンの館 " を継ぎました。館には舞台をしつらえた部屋があります。その部屋で、息子のモーリスが人形をあやつり、ショパンがその人形劇に即興で伴奏をつける…そんなこともしばしばあったそうです ...son fils, Maurice, anime un théâtre de marionnettes tandis que Chopin improvise une mélodie au piano 。
とにかくノーアンの館には、リスト、フロベール、ドラクロワ等々多くの芸術家がつどっていました。ジョルジュ・サンドは小説や戯曲や文芸批評を著すばかりか、自分の新聞社をつくるほど社会問題にかかわっていましたから、その豊かな知識と旺盛な好奇心が、たくさんの人を呼び寄せたのかもしれません。
19 世紀は、女性が夫の許可なく自分の財産を持つことも、離婚することも許されなかった時代でしたが、ジョルジュ・サンドはそれを実行しました。女性に課せらていた社会規範をなんなく乗り越え、幾人もの愛人をもったそうです... ( elle a ) ouvertement des relations amoureuses avec différents hommes 。
そしてジョルジュ・サンドは時代にさきがけて、エコロジストだったとのこと。今、フォンテーヌブローの森に 100 歳の樹齢をこえる木々が残っているのは、ジョルジュ・サンドが徹底して伐採に反対したからだそうです Si cette forêt qui abrite des arbres centenaires existe encore, c'est grâce à George Sand qui se bat bec et ongles pour la sauvegarder ... 。
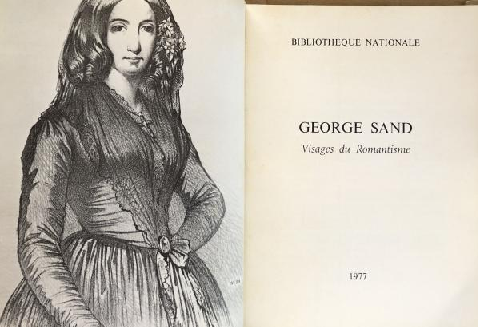
© 『フランス史のかなの「異人」たち 2 』 朝日出版社
- 上級
-
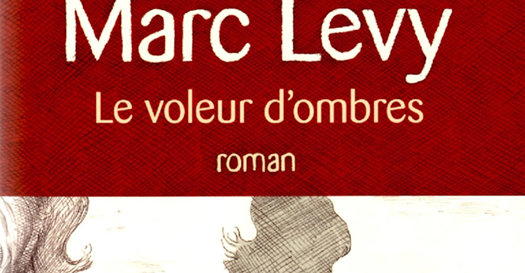
今週は『影泥棒 Le voleur d'ombres 』です。
前回は、「僕」が男の子の両親とウサギとをこっそり病院に誘導し、男の子にウサギを見せることに成功した、というくだりでした。お母さんが作ってくれたシヴェ ( ウサギの赤ワイン煮 ) を食べたのちに、自分が大切にしていたウサギを食べてしまったと考えた男の子は、それ以来、⼀切の食事を受けつかなかったのです。しかし両親が深夜に連れて来てくれたウサギを見て、男の子は再び食事を口にするようになったのでした。ただ病院にウサギを持ちこんだことが発覚し、「僕」はフェルンスタインに呼びとめられます。・・・とここまでか前回の流れ。
* * *

教授は僕に言います。「私は大まかな話ししか聞いていない。詳しくわかれば、君を罰せねばならなくなる。なので、今ではなく、いつかでよいから、私にどうしてあのような奇跡をおこすことができたのか教えてくれたまえ」と。そして「君は小児科医をめざすべきだ」と言い残して去っていきました。
次の週、僕は忙殺されていました。昼休みにソフィーがバスケットを持ってきました。男の子の両親が僕のために届けてくれたバスケットでした。自家製のサラミやパテや卵が入っていました。
とれたての卵だから、うちに来たらオムレツを作ってあげる、とソフィーは語りながらも、今だに納得がいかない様子で、「どうして男の子の心の内をききだすことができたの」と尋ねるのでした。

僕はまともな返答をするには疲れすぎていました。言葉が勝手に口をついて出ていました J'étais trop fatigué pour lui donner l'explication logique... ... ... Les mots sortirent de ma bouche sans que j'y réfléchisse... 。「男の子は何も言ってくれなかったけれど、男の子の影が僕にうちあけてくれたんだ」と。
ソフィーの反応は、かつてのお母さんと⼀緒でした。僕が屋根裏部屋で「影と話していた」と言った時、お母さんは僕を哀れむように見ていました。
しばしの沈黙ののち、ソフィーは「私たちは本当の信頼関係にないのね」と言って去っていってしまいました。僕の中の声が「ばか、追いかけろ」と言います。僕はソフィーに追いつきました。
ソフィーは「なん時間も男の子の枕元で過ごしたのに、私は男の子の声を⼀度も聞けなかった」と、いつになく、怒りを見せていました。僕は思わずソフィ―を抱きました。するとその時です。二人の影が重なり、ソフィーの影が語りはじめました。
「私は無能。何をやってもだめ。父がのぞんでいた子とはかけはなれていた。父から褒められたこともなければ、可愛がられたこともなかった…」と。
次回は p146 の " Dans l'ombre de Sophie, j'ai entendu le murmure de cette confidence et ...からです。
© " Le voleur d'ombres ", Marc LEVY, Edition Robert Laffont
